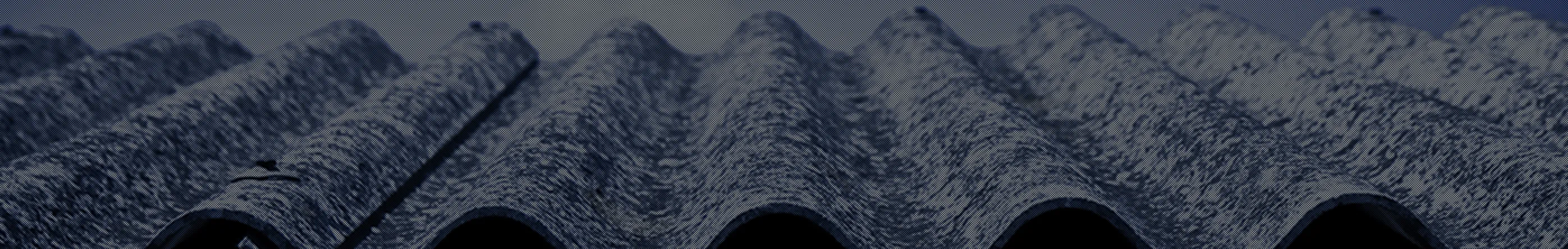
columnお役立ちコラム
アスベストの飛散性・非飛散性 | 境目と処理方法について解説
2023.04.30
アスベスト改正法により、適切な処理や手続きを怠ると罰則が科されるようになりました。
今まで以上にアスベストに対して慎重な処理が必要とされますが、この物質には飛散性があるものも存在すると知っていましたか?
アスベストはすべて飛散性のイメージがあるものですが、原状は異なります。
飛散性・非飛散性にはどのような違いがあるのでしょうか?
それぞれの特徴と処理方法などについて詳しく解説します。

アスベストは飛散性のものばかりではない?
アスベストには飛散性と非飛散性の2種類があり、それぞれ廃棄物処理の方法が異なります。
アスベストは飛散性だけと思っている方も多いですが、飛散する可能性が低い建材もあるのです。
飛散性・非飛散性の境目となる部分の判断方法を知らない方も多いでしょう。
それぞれの境目を知り、処理方法を理解して処分を行うようにすれば処分はより楽になります。
アスベスト|飛散性・非飛散性特徴と境目
アスベストには飛散性・非飛散性があります。
それぞれ、どのような特徴があるのかを以下で解説します。
・飛散性…大気中に飛び散りやすい
・非飛散性…建築解体時に飛散しやすい
主な飛散性アスベストは、吹付アスベスト・アスベスト保温材などです。
建築作業中に大気中に飛散する可能性が非常に高いものを指しています。
非飛散性アスベストに分類されるのは、成形板アスベストなどです。
建築中の飛散は少ないが、解体作業時に解体すると飛散する可能性があるものを指します。
飛散性が高いアスベストのレベルとは
飛散性が高いかどうかとアスベストレベルは深く関与しています。
ここでは、レベルの違いによる作業内容や飛散性について詳しく解説します。
| 作業レベル | レベル1 | レベル2 | レベル3 |
| 発じん性 | 著しく高い | 高い | 比較的低い |
| 作業種類 | 石綿吹付素材の除去作業 | 石綿を含有する保温材・断熱材・耐火被覆材等の除去作業 | レベル1.2意外の石綿含有建材(成形板など)の除去作業 |
| 性質 | 飛散性 | 飛散性 | 非飛散性 |
レベル1と2は飛散する可能性と発じん性が高く、作業の際には飛散防止措置が必要です。
レベル3はこれまで作業等に関する明確な方法はありませんでした。
しかし、2022年のアスベスト改正法により、現在ではレベル3のアスベストも適切な処理が必要となっています。
非飛散性アスベスト|適正処理の必要性
非飛散性アスベストはレベル3とされ、発じん性リスクも低いとされています。
それでも適正処理が必要なのはなぜでしょうか?
飛散性と共に定義・適正処理の必要性の理由などを解説します。
1.定義
環境省「非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針」では以下のように、飛散性・非飛散性アスベストの定義づけをしています。
| アスベスト成形板 | セメント、けい酸カルシウム等の原料に、アスベストを補強繊維として混合し、成形されたもののうち、アスベスト含有率が1重量%を超えるもの |
| 飛散性アスベスト廃棄物 | 吹付けアスベスト、アスベスト保温材等、容易に大気中に飛散するおそれのあるアスベストを含む廃棄物 |
| 非飛散性アスベスト廃棄物 | アスベスト成形板が解体工事等により撤去され廃棄物となったもの |
参照:『環境省(非飛散性アスベスト廃棄物の適正処理について)』
2.なぜ適正処理が必要とされるのか
1950年代~1975年までアスベストは建築資材として使われていました。
耐熱性・耐薬品製等が優れており、値段も安価であり、あらゆる現場で利用されています。
しかし、アスベストを吸い込むことによるじん肺や肺がん中皮腫などの病気を引き起こす可能性が高い有害物質であるとわかりました。
製造の禁止・取扱いの注意などが決められ、2009年にはアスベストが全面禁止となりました。
現在は、建築に一切使用されていません。
しかし、使用されなくなった現在でもアスベストを使用した建物は残っています。
そのため、解体時に適正処理が必要です。
3.計画から最終処分まで行うことが求められる
アスベストを飛散させず安全に処理をするために、計画から最終処分まで行うことが求められます。
アスベストが含まれている可能性が高い建物は、解体作業前にアスベスト調査が必要です。
調査結果は自治体等に報告し、アスベストが含まれている場合には、レベルに合った処理方法で処理・廃棄が義務づけられます。
適切な処理をしたかの書類なども提出せねばなりません。
違反をすると罰則もあるので、報告は必ず行いましょう。
飛散性アスベスト|適正処理の方法
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」を基に適切な処理を行う必要があります。
| 作業レベル | レベル1 | レベル2 | レベル3 |
| 廃棄区分 | 産業廃棄物 | 産業廃棄物 | 産業廃棄物 |
| 処理方法 | 遠隔工法
作業場所を養生シートで隔離し、集じん装置で作業場所を負圧に保ったうえで作業する 作業後も集じん装置は24時間稼働させる |
集じん・排気装置の稼働
抑制剤による湿潤化 抑制剤の効果を確認後、ケレン棒等により吹付けアスベストを掻き落とす 吹付けアスベスト除去面に粉じん飛散防止処理剤を散布する |
養生シートで隔離
作業部付近の湿潤化 薬液等の使用 除去作業 |
| 保護衣の着用 | 必要 | 必要 | 必要 |
レベルが高くなるほどアスベストが飛散しやすいので、飛散させないための適切な処理が必ず必要です。
飛散性アスベスト|処理費用を抑える方法
アスベストは特別な処理方法や運搬・廃棄処分が必要になるので、通常の廃棄物処分費用よりも高額になってしまいます。
アスベストの処分費用だけではなく解体費用もかかるので、できるだけ費用は抑えたいと思う場合には、自治体等の補助金を利用しましょう。
国土交通省yが管轄する補助金の場合、公共団体を経由して申請が可能であり、原則として一棟当たりの上限は25万円です。
まとめ
アスベストの飛散性・非飛散性の特徴とそれぞれの処分方法などについて紹介しました。
アスベストは吸い込んでしまうと肺がんやじん肺、中皮腫などの重大な病気を発症してしまう可能性が高く、適切な処理が求められています。
この物質には飛散性・非飛散性の2種類があり、それぞれ適正処理方法が異なっています。
適正処理を行わないと、罰則が科せられてしまうので適正処理が必要です。
素人が判断処理するのはとても難しいので、専門業者に依頼をして適切な処理を行ってもらいましょう。



